BOØWY好き必見!BOØWYを10倍楽しく聴ける本「大きなビートの下で」

「大きなビートの下で」は氷室、布袋、松井、高橋それぞれの幼少期から書かれた本です。当時BOØWYの情報は今ほど溢れてはいなくて、もちろんユーチューブもなければ、携帯電話も普及されていない時代、、、。
BOØWYはメディアにもあまり出なかったし、ライブビデオが5本市販されているくらいでした。そのライブビデオも氷室がMCしているところもなく、本当にライブのみを楽しむというものでした。
私がボウイを知った時にはすでに解散していたので、いくら好きでも生では見ることができなかったのでとても悔しい思いをしました。
そうした中でこの「大きなビートの下で」は私からすれば本当に貴重な資料となりました。
41歳の私より若い方は当然BOØWYを見ることができませんが、この記事を読んで少しでもBOØWYが出来るまでのことを知ってもらえれば嬉しいです。
氷室 京介
活発な少年、氷室。小学生の氷室は遊びとイタズラの区別ははっきり理解していたにも関わらず、クラスメイトに対するイヤガラセの犯人と担任に疑われて酷く傷つく氷室。母か担任に呼び出されても、氷室はそんなことするわけがないと言い切れる強き母親が描かれている。
中学生になればカッコいいと思ってたツメ入りの学ランをまとい規定通りの丸刈りで毎日学校に通う。学校は仲間といれるので楽しかった。しかしちょっとしたイザコザから2年先輩の三年生と喧嘩になるが、3対1でも負けない氷室。
そこからは、わかりやすく解決出来る喧嘩を好み、バイクに跨がり、暴走族に入る。
喧嘩した後に必ず自分の名前を言うのが、またカッコいい!!「俺は県立の氷室だ!何かあったらいつでも来い!」
しかし、それも何か違うことを感じていたころ、キャロルの解散ライブをTVで目にする。姉のアコースティックギターで遊んだことがある氷室は昔ギターで一緒に遊んでいたの友人、菊池と松井とよく連むようになり、バンドを組むようになる。
菊池がギター、松井がベース、氷室がドラムだ!
確かにBOØWYでデビューしてからも一度ライブで氷室ドラム、松井ギター、布袋ベース、高橋ボーカルでシンフォニックをしたことがある笑
氷室がお茶目に「今日くらい良いよね笑」とか言いながら、、、今でもユーチューブに残っているんじゃないでしょうか。
話は戻り菊池の友人、福田アキラがドラムに入り、氷室がボーカルとなる。
サウンドがピタリと合った快感は氷室にとって喧嘩やバイクのそれによく
似ていたけれど、大きくどこか違っていた。
氷室は歌うことにポリシーがあり、自分が納得出来るものだけを演奏していくことを決め、バンド名は英和辞典から探した「デスペナルティ」となる
地元の人気バンド「ウィークリー」のボーカルが「氷室よりうまいかもよ」と
松井が煽るが、氷室は「こんなやつがナンバー1」ならすぐに抜き去る自信があった。
実際すぐに同じくらい「デスペナルティ」は人気がでて、コンテストに出ることになる。
「EAST WEST79」というコンテストには「ウィークリー」ともう一つの人気バンド、布袋が所属していた「ジギーリギー」が解散して新しく出来たバンド「BLUE FILM」も出場することになっていた。
「デスペナルティ」はわずかな差で「BLUE FILM」を押さえ全国大会へといき、そこでも入賞を果たした。
そこからレコード会社から誘いを受けて、とうとう上京である。
ただ、「実力不足」を理由にメンバーをバラバラにさせ、氷室は「スピニッジ」というバンドに入れられるのであった。
そこでは、嫌というほど大人のルールに縛られ辛い経験をする、、、。
松井恒松
先頭に立って歩くよりも、少しだけ後に下がったポジションが合っているということに気付いたのは何歳だったろうか、、、
小学生の松井はいつも一番声が大きく教室の中を駆け回るうちの一人だった。
しかし、ちょっとしたイザコザから松井は「動」から「静」に変わる。
ただし、目立たない「静」では決してない。
一つの決めごとの中で、自分のポジションがはっきりした時に、松井はまるで機械のように正解になり、自分の意見を曲げることはなかった。
そして、中学2年の終わり頃、友人の菊池が家に氷室を連れてきた。
氷室とよく連むようになるが、いつもヒヤヒヤしていた。こうすればこうなると考える松井の常識的な考えを、いつも氷室は飛び越えて事をおこす。
けれども気付いた時、氷室は氷室でいつでも、何でも松井に聞くようになっていた。
「これでいいと思う?松井はどう思う?」
高2の時にバンド(デスペナルティ)を組み、音楽が一番好きな遊びになった。後に自分がベースを担当し、氷室がボーカル、氷室と菊池がオリジナル曲を作り始め、そこにはもう「CHU-RU-RU」の原型、「CHU-LU-LU」があった。
松井はヤマハのコンサートを見に行った時に「ウィークリー」のボーカリスト「土屋」が目立つ存在だったから、氷室が見たらどう思うか、、、。会わせてみよう、、、何だかそうするのが、とても楽しく思えた。。
それから1年たった夏の「EAST WEST79」というコンテストで、布袋が所属する「BLUE FILM」を押さえることに成功する。そして上京。松井は事務所の手によって「9thイメージ」のベーシストへ形を変えてしまう。
「9thイメージ」はバンドとして、すでに順調なすべり出しを約束されていたけれど、松井の気持ちらどこかで狂い始めたことを感じていた。
何か大切なこと、、、を見失いそうな気がしていた。
高橋 まこと
高橋はギターを持っていつも大好きなジョン・レノンのパートを演っていたけれど、中2の夏にドラムを購入し、たった一人のドラマーとして、友人の家に遊びに来る全てのドラムスを務めることになる。
高校の文化祭にビートルズのコピーバンド「ホワイト・スクール」でトリをつとめる。一曲目は「CAN'T BUY ME LOVE」ステージも中盤にさしかかると、半分以上の客が頭の上に拳を上げていた。最高潮ー!
ただドラムスを叩くだけじゃなく違う楽しみがあることに、高橋は気付いていた。ボーカル、ギターリスト、ベーシストの後ろ姿と、観客の顔を見ながらのドラムスが、そしてバンドというものが、こんなに楽しいものなんだということを、理屈抜きに体で感じていた。
高校を卒業し、叔父の仕事を手伝いながら「暗殺剣」というバンドに加入し仙台ナンバー1と呼ばれていた。
しかし、解散をきっかけに上京する
布袋 寅泰
7歳の時にすでに母の為にピアノで「ありがとう」という曲を作り、誕生日会で披露し中学へ上がるまで、ピアノのレッスンを繰り返すことになる。
中学2年で初めてギターを手にし、大好きだった海水浴への興味を失わせた。その後、母の財布から1万円失敬してギターとアンプがセットになっているもの手に入れる。
布袋は三大ギタリスト(エリック・クラプトン、ジミ・ペイジ、ジェフ・ベッグ)よりマーク・ボランやデビッド・ボウイを好んだ。
ピアノから入った布袋にとって、初めからギターソロとかギタリストとかへの頑なな意識はなかった。いいものはいい。好きなものは好きだ。
人の事を否定しないかわり、自分のことは誰よりも頑なだった。周りのギタリストが速弾きを見せ合う中、布袋だけは体中でギターを弾いていた。
そして、どこで知ったのか林田が声をかけてきた。
林田は「キティ」というバンドを組んでいた。そこにはギタリストがいなかったので、ギタリストとして加わることになる。
高校に入った頃には身長が180cmまで伸びていた。林田3年生。布袋1年生。
林田の卒業と共に、布袋は新しく同じ歳でバンドを作ったのが「ジギーリギー」
ボーカルにクラスメイトの上野、ベース、ドラムは隣のクラスから、テナーサックスはクラスメイトの深沢に頼んだ。
身長はその頃、止まった。190cmに届いていた。
「ジギーリギー」は全員がメイクアップし、190cmのギタリストが踊りながらプレイする。
演奏だけでなく、見せるインパクトとシャープなギターリズムで、少しずつ林田がいたバンドの「キティ」の噂を超えていった。ただしそれは「ジギーリギー」ではなく、布袋個人に対する評価だったかもしれない。
ギターソロをあまり演らない布袋の否定論と、とにかくかっこいいという両極端な二つ。
布袋という名前は、その苗字と190cmの身長も手伝って、あっという間に小さなロックシーンに広がった。
高2の夏、ヤマハホールで「ウィークリー」と出会う。布袋は「ウィークリー」とやり合うことになると直感し、拳を使わない喧嘩をそこのボーカル土屋に売りに行く。
「初めまして!そのうち一緒に演ると思いますが、その時までは頑張ってください。きっと僕たち勝ちますから!よろしく!」
頬のこけた土屋は上を見上げて言う
「布袋くんでしょ、知ってるよ。この間の体育館のやつ見てたんだ。すっげぇかっこいいね。俺、好きだよ」
これが布袋と土屋の出会いだった。
二人の付き合いは、それからずっと続くことになる。同じバンドで、そして友人として、さらにBOØWYのマネージャーとして、、、。
布袋のいる「ジギーリギー」、土屋のいる「ウィークリー」、氷室のいる「デスペナルティ」が高碕の中で活発に活動し、ホールはどれか一つのバンドが出演していれば超満員になる時代を迎える。
そして、たった一度の3バンド共演を最後に3バンドから2バンドになる。「ウィークリー」に布袋が参加し「BLUE FILM」になる。
コピーはやめて、オリジナルを演りコンテストを皮切りに東京へ出ることを目論んでいた。
音楽で食べていきたい。
ロックをやって行く上で、布袋と土屋の二人はお互いを最高のパートナーと認め合っていた。
コンテスト「EAST WEST」ではデスペナルティとの決着が着く。
「わずかな差だったよ」と審査員は笑った。
勝利の女神は「デスペナルティ」に微笑んでいた。。
翌年の春、布袋と土屋だけが東京に向かったが、土屋は歌うことからきっぱりと足を洗ってしまった。布袋は時々たのまれるスタジオの仕事や、作曲を思いつく時間よりも、カウントで始まる仲間たちとのバンドをしたい気持ちが勝ちはじめていた。
BOY TO BOØWY
氷室はこの街も、業界というところも自分の性に合っているとは思えない。
好きな事を嘘までついて金にするのではなく、好きだからこそ、好きなようにやっていきたいと考えていた。
疲れたんだ、、、
田舎に帰ろうとおもった。
田舎に帰る当日、RCサクセションのライブを見てから帰ろうと日比谷へ。
会場に来ている何千人もの若者が、RCの、そして清志郎の登場するのを待ちわびていた。
夕暮れの中、男たちのシルエットが浮かんだ。
「ようこそ!」
清志郎の一声で、バラバラだった5千人が一つになっていた。
驚いた、悔しかった。
理屈も感性も通り越し、素直に感動した。
ここを捨てようと荷物肩にかけていた自分に腹が立っていた。
ラストの曲を待たずに地下鉄へ向かった。
氷室の頭の中には、一人の男の顔が浮かんでいた。
やり直すんじゃない、ここから始めるんだ!
布袋 寅泰。
まともに言葉を交わしたことすらない。人伝てに聞いた電話番号で会うことが出来た。
二人とも少しだけ念入りにメイクをし、待ち合わせの場所に向かう。
六本木で二人のBOØWYが出会った。
喫茶店で氷室は結論から話しはじめる。
ロックをやりたいこと。
バンドをやりたいこと。
それは仲間でなければいけないこと。
本当にやりたいことをやっていきたいということ。
決まったら専ら動くのは早い。
氷室は感じてるそのままを社長に話した。
「スピニッジ」をやめたいこと。布袋とやっていきたいことを。
二人はその足で氷室の家へ向かい、お互いのオリジナルを確認する。
「まずは布袋の曲を入れよっか?」
「サビはこれだね。」
リフをビートで刻む。
「イメージダウン」のフレーズだ。
氷室がノートに走り書きを始める。
二人の共作がこの瞬間から始まった。
氷室の歌詞には政治も反体制も、全く存在しないい。こうしなさいというような説教臭いメッセージ性もない。
歌いたいことを歌う。
人がなんと言おうと、思っているとおりのことを言葉にしていくだけ。
ファーストアルバム「モラル」の言葉たちには、バンドをつくる以前から結成するまでの氷室の心が、ストレートに言葉になって踊っている。
ひと月が過ぎようとしていたが、二人は録音作業を繰り返していた。
「アイツに下手な曲は聴かせられない、、、」
例え5曲できても、テープに入れるのは自分が気に入った2曲だけだった。
これならきっと驚くはず、、、この曲なら絶対、まいっちゃうはず、、、
こんな二人の競作は
「ノー、・ニューヨーク」「ゲリラ」「ギブ・イット・トゥ・ミー」もあった。
メロディを嘘っぱちな英語が追いかけ、氷室は全く酒をが飲めなかったので、コーラを。布袋はビールを飲みながら作業は続けられた。
収入源がないため、
「金」の問題が発生した。
「ご飯どうしよっか、、、」「お腹ちょい減りましたねぇ、、、」
なけなしの千円でコンビニに出かけ、二人は計画的に食べるようにしていた。
「こっちの方が長持さもちするよ」
「でも、それはまずいぜ」
こんな生活だったが、二人は進ませなければならないことが順調な上、二人でいることが楽しかったから。
お金なんて何とかなる。寝るのも忘れ、食べるのを忘れ、ひとつのことを考えている時は苦にはならなかった。
曲は「モラル」に収められている「イントロダクション」と「エンドレス」以外と数曲がすでにテープに収められていた。
メンバーを見つけなければいけない。
布袋が貼り紙を考える。
シンプルな白い紙に「Ø」空集合の記号が書いていた。
誰にも似たくない。
どこにも属させない。
ベース、ドラムス募集の文字。
二人は日払いでギャラをくれるバイトを始め、ライブハウスのロフトや屋根裏にチラシを貼らせてもらった。
すぐに十二人から連絡があり、セッションすることになる。曲は「ノー、・ニューヨーク」
どんなやつかわからない、、、。
かなり出来るヤツだとしても、気の合うヤツがいるだろうか、、、。
結果は散々だった、、、やたらと弾きすぎてリズムがガタガタなやつ、テクニックをひけらかすやつ、話にならないドラマー、格好と口だけのヤツ、、、布袋をうつむかせ、氷室を無口にするには充分だった、、、
6日目のセッションも気分が重く終わった。
氷室の家で電話がなる。
「セッションなら断るからな、、、」
布袋は何も言わず、そっぽを向く。
突然、氷室の笑い声がした!
電話の相手は「デスペナルティ」のベーシスト、松井恒松からだった。
松井は「織田哲郎&9thイメージ」で充実した活動を行なっていた。
受話器を置くと氷室は煙草に火をつける
いい知らせの時、いつも氷室はすぐ話そうとしない。しかし、今回に限ってはあまり待つ必要がなかった。
「松井がね、やりたいんだってよ、俺たちと。」
我慢しきれない氷室がすぐに口を開いた。
上半身を起こして布袋が氷室をみる。
仲間とバンドを演りたい、お金にならなくてもいいことを氷室に言っていた。
「俺じゃダメかな、、、」
松井らしい伝え方が氷室は好きだった。
松井なら全く問題はなかった!
松井は二人のオリジナル曲を、友人であることを全くぬきにしても、一発で気に入ってしまい、二人の才能を素直に認めてしまっていた。
もっと驚いたことは、二人ともベースが上手いことだった。
松井がほとんどの曲をマスターし終える頃、氷室が一人の男をスタジオに連れてきた。
「スピニッジ」のドラムの木村だ。
息のつまりそうなスピニッジの中で木村だけはウマが合い、いろんな意味で自分よりも大人の部分を持った木村を氷室は好きだった。
プロデューサーになりたい木村にドラムをやって欲しいと頼み込んでいた。
「ドラマーとしてではなく、プロデュースをしてみたいという眼で氷室を見続けていいか?」
それが木村の返事だった。
1981年10月。
言葉こそ乗っていなかったが、
「エリート」「ラッツ」「オンマイピート」達がバンドの音へと変わっていく。
しかし、4人になってから1週間もしないうちにトラブルが訪れた。
今までのロックスタイルとは、アレンジもギターワークも大きく違うこと。ずっと音楽をやって来た木村にとって、布袋のスタイルをすぐに受け入れられなかった。
布袋のギタースタイルにはソロパートやギター・メロディとドラムスのせめぎ合い、ブルース、まとわりつくギターフレーズも全くなかった。
木村は布袋のギターで本当にいいのか?と確認を求めた。
氷室の感性は布袋のギターを求めていた。単純に「かっこいい」と思っていた。
「あれでいいんです」
かたや布袋からは木村のドラムのパワー不足を指摘してきた。氷室はディスコ調のバンドをやって来た木村に手数よりもパワーを求めても不可能なことだとわかっていた。
その後、布袋はサックスを入れることを提案し、「ジギーリギー」でやっていた「深沢」を、氷室はサイドギターをと「諸星」を連れてきた。
バンド名こそまだなかったものの、第一期のBOØWY達が初めてスタジオ内に顔を合わせたのだ。
始まりの始めが、もう目の前に迫っていた。
当初、感じていたギタリストへの不安もサウンドが固まるにつれて、解消されていた。
いいバンドだ。
木村はお世辞抜きでそう思っていた。
テープに録音されたラフな曲は松井のダウンピッキングも、布袋の空間を捻じ曲げてしまうギターワークも、ほぼ完成され、歌詞も氷室か深沢が乗せていた。
「音に残そう!」
その録音したテープを持って、数ヶ月ぶりに事務所へ向かう。
社長がテープのスイッチを押す。
一発目からKOパンチ!
「ノー・ニューヨーク」だ。
社長の表情はかわらない。
氷室は見逃していなかった。
爪先でリズムを取っていた社長が曲が進むにつれて、膝でリズムを取り出していたのを、、、。
正式なレコーディングとライブが決まった。
バンド名には拘りはなかったが布袋は「Ø」を使いたがっていた。
男ばかりだから「BOY」でいいんじゃないか?
事務所から来たマネージャーってヤツが口を開いた。
でもそれだけじゃ芸がない、、、
単語を作っちゃえ!
「BOWY」真ん中にØを入れて「BOØWY」に決まった。
けれど、レコーディング資料の方のチラシには「暴威」の文字で印刷されていた、、、。
アルバム「モラル」のレコーディングは順調だったが、音をきちんとした形にしていくにつれ、ビート感のズレがはっきりと見え始めた。
松井と木村のコンビネーションもうまくいかなかった。木村はドラムスのオーディションを提案する。
ドラムスのオーディションはロフトでの席だった。
客はまだゆっくりと数えれば、全部数えられるくらいしか入っていなかったけど、ライブの度に右手を振り上げる連中も増え出していた。
そして、ドラムスオーディションのチラシを見た一人の男が、くいいるようにBOØWYのビートを確かめていた。
本当の始まりが、始まろうとしていた。アンコールが全て終了し、自分たちと同じように焦るまみれになった男が楽屋に訪ねてきた。
男の名を「高橋まこと」といった。
読み終えて
この本では高橋まことがオーディションに来たところで終了します。
もしかしたら、今からがいいとこだったのに!!と思う方もいるかもしれません。
だけども敢えてここまでというところがいいんですよー(^^)/
高橋まことはこのオーディションで「カウントの声のでかさ」「やたら走るリズム」それがBOØWYにあっていて「決め手」となったようです。
結成されてからは色んな雑誌や対談でも話されているので貴重な幼少時代や「暴威」時代のことが知れてとてもおもしろいです。
ご紹介させていただいた部分はほんの一部ですので、本には恋愛のことや、喧嘩のこと、ちょっと危ない話、などなど細かく書かれていてBOØWY結成までの経緯がとてもわかりやすくおもしろいです。
これを読めば本当にBOØWY通間違いなしです!
ぜひ、読んでみてくださいね。
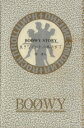
【中古】 大きなビートの木の下で BOOWYストーリー /紺待人(著者) 【中古】afb
- ジャンル: 本・雑誌・コミック > エンターテインメント > 音楽 > その他
- ショップ: ブックオフオンライン楽天市場店
- 価格: 1,045円